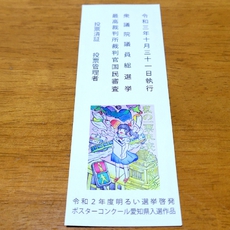2013年09月04日
地域防災訓練レポ
防災の日であった9月1日(日)、我が街も地域ぐるみの防災訓練が小学校で行われました。
消防署と消防団の車両もスタンバイ完了。


自治会の自主防旗もズラリと並んでいます。

開会式の後、まずは緑政局が道路上の倒木を除去する訓練。チェンソーで手際よく切断していきます。

こちらは煙体験トンネル。タオルやハンカチを口に当て、なるべく這うように進みます。

おっ、給水車が到着しました。ポリタンクを持った市民が給水を受けます。

その水を使って炊き出しの訓練。

お米を炊飯袋に入れて、梅干しも投入します。

これが炊飯袋に書かれたごはんの炊き方の説明。

袋の口をしっかり輪ゴムで縛り、大きな非常用炊飯具の釜の湯に投入します。


炊き上がったごはんをざるに上げます。説明書きには30分とありましたが、訓練では45分間お湯で蒸していました。このごはん、試食しましたが梅干しの塩味が広がって、それなりに美味でした。

この訓練を行った小学校の海抜は33m。海から10Km以上離れているので、ハザードマップでは津波の危険はないことになっています。我が家は海抜45mぐらいなので、もう少し安心かも。

名古屋市の全小学校にはこのような非常時自主給水のできる設備があります。

小学校の防災倉庫にある給水ツールセットを使い、鉄の蓋をバールで開けます。

すると4つの水道の蛇口が。上水道の本管から耐震管でつながっているので、ほぼ壊れることはないとのこと。蛇口を開けてホースを繋ぎ、3分程放置。溜まっていた水が抜けたところで給水ツールセットに入っている試験薬で塩素量を計り、飲用に適しているがチェックしてから利用します。

一方その頃、救援物資が到着。避難住民が一丸となって、バケツリレー方式で避難所に運び込みます。


こちらは展示コーナー。各家庭で支度しておくべき防災用品や非常食が並べられています。よく、水は1人1日3㍑と言われますが、夏場は5㍑は必要だとか。しかもこれは飲用や調理用で、生活水は含まれていません。以前は3日間分の備蓄を、と言われていましたが、今は1週間分が推奨だそうです。

100円ショップで売られている物も、防災用品として立派に役に立ちます。要は工夫次第ということです。

簡易式の手作りトイレ。長めのポンチョやカッパを使えば、女性も恥ずかしい思いをしないですむという豆知識も。

便器は植木鉢スタンドとバケツ、便座は段ボールを何層か重ね貼りして便座カバーをかけています。バケツの中には不透明な袋と簡易トイレ用凝固剤を入れます。それらは可燃ごみとして処分するそうです。

ボランティアセンターも避難所に開設されます。自分のできることを申告し、ニーズに合ったところに自分の名前を書いた付箋を貼り、傷害保険に入ります。例えば、小さな子供と遊ぶのが得意だとか、お年寄りと話すのが好きだとか、車イスを押せるとかでも、立派なボランティアになります。

保健所の保健師さんによる、怪我の応急手当の講習。三角布の使い方や、他人の血液から感染症にならないためにビニル袋を上手く使う方法の実演がありました。

消火器による模擬消火訓練。消火液ではなく今回は水が入っていました。高圧ですが、けっこう短時間しか噴射できないので、ターゲットに上手当たるようにしなければなりません。

こちらはバケツリレーでの消火訓練。バケツを渡すときは必ず「ハイッ!」と声を掛けて渡すのが鉄則。また、逆回りで回ってくることもあるので、右利き左利きに関係なくリレーできるように、とのアドバイス。

さあ、ここからは消防士や救急隊も登場です。災害現場に指揮本部を設営します。

そして救護やトリアージを行うテントを設営。エアボンベで一気に柱を立ち上げ、およそ2分半で設営完了。


損傷した車に閉じ込められた人を、スプレッターでこじ開けたドアから救出。ストレッチゃーでテントに運ばれます。


テント内では、保健師や救護医師による応急手当が行われる一方、トリアージにより救急搬送の優先順位を決めます。残念ながら零(黒色)の判定の人は、順次安置所に運ばれていくそうです。実際に阪神淡路大震災や東日本大震災で現地入りしたスタッフから、説明を受けました。

これが搬送されてきた人たちの容態一覧ボード。出産間近の設定の人もいます。

最も優先的に治療の必要がある患者が、救急車で南医療病院に運ばれていきました(という仮定)。

最後に消防団による放水訓練。女性の団員もいるんですね。会社勤めだと勧誘されてもなかなか入団できないんですよね。本当は他人任せではいけないんだけど…。

およそ2時間に亘る訓練も終わり、閉会式を行い解散となりました。直後に大粒の雨が降りだしました。

ちなみにこれ、名古屋市消防局に2台所属するウニモグの後方支援車。隊員の更衣や食事、休憩を担う車両です。エアクリーナーもルーフ付近まで延長され、渡河もできる頼もしい車両です。4駆好きのワタシにはいつまでも現役でいてほしい消防車両ですが、残念ながらディーゼル規制で年末で代替えになってしまうそうです。

今回、地元自治体の防災訓練を見に行ったのは初めてでした。自然災害が多発する昨今、まず自分の身は自分で守り、次に自助努力でお互いに助け合い、率先して自分のやれることを申し出て被害を最小限に食い止める、それが住民としての義務であり責務であると思いました。
また、普段はレジャーとして楽しんでいるキャンプも、非常時にはそのノウハウが活きてくるとつくづく感じました。
あってほしくないことではありますが、いずれ今回の経験が役に立つ日が来るでしょう。皆さんも一度、このような防災訓練に参加したり、見学をされてはいかがでしょうか?キャンパーなら必ず、有事の際に自身のやれること、役に立つことが見えてくると思います。
大災害に行政の助けはなかなか来ません。自分達で生き延びる術を考えておく必要がありますね。
消防署と消防団の車両もスタンバイ完了。


自治会の自主防旗もズラリと並んでいます。

開会式の後、まずは緑政局が道路上の倒木を除去する訓練。チェンソーで手際よく切断していきます。

こちらは煙体験トンネル。タオルやハンカチを口に当て、なるべく這うように進みます。

おっ、給水車が到着しました。ポリタンクを持った市民が給水を受けます。

その水を使って炊き出しの訓練。

お米を炊飯袋に入れて、梅干しも投入します。

これが炊飯袋に書かれたごはんの炊き方の説明。

袋の口をしっかり輪ゴムで縛り、大きな非常用炊飯具の釜の湯に投入します。


炊き上がったごはんをざるに上げます。説明書きには30分とありましたが、訓練では45分間お湯で蒸していました。このごはん、試食しましたが梅干しの塩味が広がって、それなりに美味でした。

この訓練を行った小学校の海抜は33m。海から10Km以上離れているので、ハザードマップでは津波の危険はないことになっています。我が家は海抜45mぐらいなので、もう少し安心かも。

名古屋市の全小学校にはこのような非常時自主給水のできる設備があります。

小学校の防災倉庫にある給水ツールセットを使い、鉄の蓋をバールで開けます。

すると4つの水道の蛇口が。上水道の本管から耐震管でつながっているので、ほぼ壊れることはないとのこと。蛇口を開けてホースを繋ぎ、3分程放置。溜まっていた水が抜けたところで給水ツールセットに入っている試験薬で塩素量を計り、飲用に適しているがチェックしてから利用します。

一方その頃、救援物資が到着。避難住民が一丸となって、バケツリレー方式で避難所に運び込みます。


こちらは展示コーナー。各家庭で支度しておくべき防災用品や非常食が並べられています。よく、水は1人1日3㍑と言われますが、夏場は5㍑は必要だとか。しかもこれは飲用や調理用で、生活水は含まれていません。以前は3日間分の備蓄を、と言われていましたが、今は1週間分が推奨だそうです。

100円ショップで売られている物も、防災用品として立派に役に立ちます。要は工夫次第ということです。

簡易式の手作りトイレ。長めのポンチョやカッパを使えば、女性も恥ずかしい思いをしないですむという豆知識も。

便器は植木鉢スタンドとバケツ、便座は段ボールを何層か重ね貼りして便座カバーをかけています。バケツの中には不透明な袋と簡易トイレ用凝固剤を入れます。それらは可燃ごみとして処分するそうです。

ボランティアセンターも避難所に開設されます。自分のできることを申告し、ニーズに合ったところに自分の名前を書いた付箋を貼り、傷害保険に入ります。例えば、小さな子供と遊ぶのが得意だとか、お年寄りと話すのが好きだとか、車イスを押せるとかでも、立派なボランティアになります。

保健所の保健師さんによる、怪我の応急手当の講習。三角布の使い方や、他人の血液から感染症にならないためにビニル袋を上手く使う方法の実演がありました。

消火器による模擬消火訓練。消火液ではなく今回は水が入っていました。高圧ですが、けっこう短時間しか噴射できないので、ターゲットに上手当たるようにしなければなりません。

こちらはバケツリレーでの消火訓練。バケツを渡すときは必ず「ハイッ!」と声を掛けて渡すのが鉄則。また、逆回りで回ってくることもあるので、右利き左利きに関係なくリレーできるように、とのアドバイス。

さあ、ここからは消防士や救急隊も登場です。災害現場に指揮本部を設営します。

そして救護やトリアージを行うテントを設営。エアボンベで一気に柱を立ち上げ、およそ2分半で設営完了。


損傷した車に閉じ込められた人を、スプレッターでこじ開けたドアから救出。ストレッチゃーでテントに運ばれます。


テント内では、保健師や救護医師による応急手当が行われる一方、トリアージにより救急搬送の優先順位を決めます。残念ながら零(黒色)の判定の人は、順次安置所に運ばれていくそうです。実際に阪神淡路大震災や東日本大震災で現地入りしたスタッフから、説明を受けました。

これが搬送されてきた人たちの容態一覧ボード。出産間近の設定の人もいます。

最も優先的に治療の必要がある患者が、救急車で南医療病院に運ばれていきました(という仮定)。

最後に消防団による放水訓練。女性の団員もいるんですね。会社勤めだと勧誘されてもなかなか入団できないんですよね。本当は他人任せではいけないんだけど…。

およそ2時間に亘る訓練も終わり、閉会式を行い解散となりました。直後に大粒の雨が降りだしました。

ちなみにこれ、名古屋市消防局に2台所属するウニモグの後方支援車。隊員の更衣や食事、休憩を担う車両です。エアクリーナーもルーフ付近まで延長され、渡河もできる頼もしい車両です。4駆好きのワタシにはいつまでも現役でいてほしい消防車両ですが、残念ながらディーゼル規制で年末で代替えになってしまうそうです。

今回、地元自治体の防災訓練を見に行ったのは初めてでした。自然災害が多発する昨今、まず自分の身は自分で守り、次に自助努力でお互いに助け合い、率先して自分のやれることを申し出て被害を最小限に食い止める、それが住民としての義務であり責務であると思いました。
また、普段はレジャーとして楽しんでいるキャンプも、非常時にはそのノウハウが活きてくるとつくづく感じました。
あってほしくないことではありますが、いずれ今回の経験が役に立つ日が来るでしょう。皆さんも一度、このような防災訓練に参加したり、見学をされてはいかがでしょうか?キャンパーなら必ず、有事の際に自身のやれること、役に立つことが見えてくると思います。
大災害に行政の助けはなかなか来ません。自分達で生き延びる術を考えておく必要がありますね。